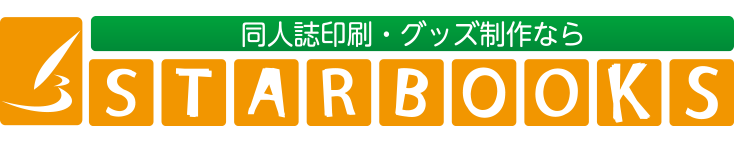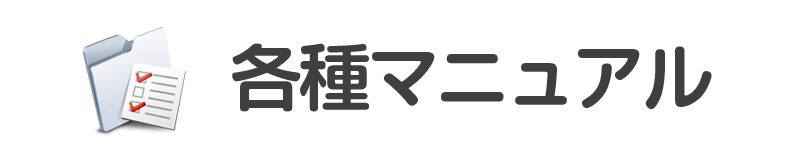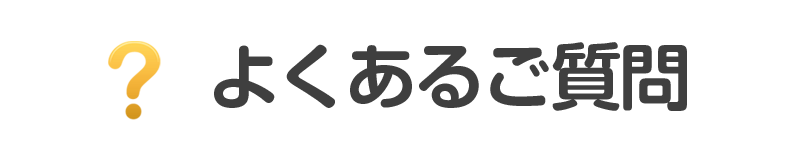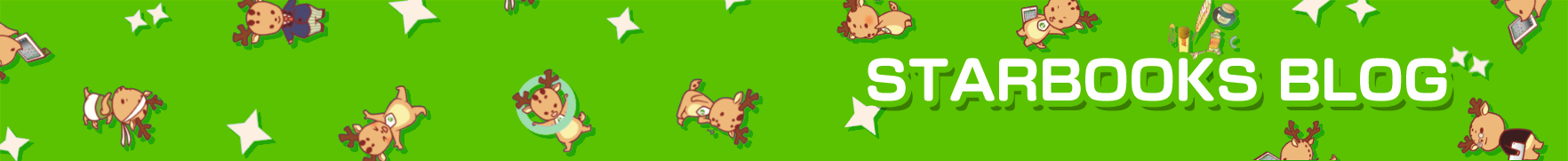2025年1月18日

STARBOOKSをご愛顧いただきましてありがとうございます。
STARBOOKSはご発注後に、ページ数など仕様変更できることも特徴の一つです。
「いつも本文入稿までにページ数が定まらない」
「発注のページ数に合わせて、無理に1ページの文字数を増やしたら読みにくくなった」
「先に表紙をデザインをお願いしたいけど、もしかしたらページが変わるかも?」
ページ数の増減で困ることってありますよね。
今回は、表紙と背表紙と裏表紙を別々で作ってご入稿する方法についてご紹介いたします。
|目次
・どんなデザインになるの?
・表紙、裏表紙の作り方
・背表紙の作り方
・プラス情報
・まとめ
どんなデザインになるの?
表紙と背表紙と裏表紙が別々って、どんなデザインになるの? と思われるかもしれませんが、以下のようなライトノベルや文庫本のようなデザインをイメージしてください。
表紙にイラストとタイトルロゴがあって、背表紙にタイトルと著者名、後ろにあらすじやロゴマーク、バーコードがあったり……。

もちろん、表1(表紙)・表4(裏表紙)を含めた1枚のテンプレートで作成をいただいても構いません。
ですが、作成環境によって中央がどこかうまくガイドが引けない……背幅が確定しないから表紙のイラストを発注できない……などの悩みを抱えていた方はあらかじめ別で表1(表紙)・表4(裏表紙)を作って(頼んで)おいて、最後に背表紙だけ作成するというのもテクニックのひとつとなります。
注意するのは以下のひとつだけ。
「表1・背表紙・表4をまたぐデザインはしない」……イラスト、パターンなどを繋げない。
別々のデータをSTARBOOKSの方で合体させることになりますため、
一つのデータで絵柄が完結する形でデザイン・作成を行なってください。
表1の続きが背表紙にあったり、ひとつのイラストを分割して配置したりするとうまく合体できません。気をつけてくださいネ。
また、詳しい作成方法はこの後の章でお伝えいたしますが、作成の際に注意すべき点をもう一つ。
「中央合わせは各データごとで行う」
STARBOOKSのデータは
トンボが必須ではございません。
そのため、
デザインは各データの中央に配置するようにお願いしております。
そうでないと、どこを基準に印刷をすれば良いのかがわからなくなるからです。
入稿の際の名前付けも重要です。
「h1」「se」「h4」など、どの部分のファイルかわかるように名前をつけてください。
出版社さまのレーベルのようにサークル独自のデザインで発行し続けたり、続き物で背表紙の絵をつなげたりするのもこちらの作成方法ですと作りやすいかもしれません。
では、次の章で早速作り方を見ていきましょう。
表1(表紙)、表4(裏表紙)の作り方
表紙と裏表紙の作り方は簡単です。
作りたいサイズのテンプレートを利用していただくか、ご自身で作りたい実寸サイズ+塗り足し天地左右3mmずつ足したドキュメントを作成いただければ問題ありません。
それぞれのパターンに分けて確認していきます。
【テンプレートを利用していただく方法】
テンプレートは、ご発注サイズの「カラー本文(単ページ)」を使用していただく形になります。
↓↓↓テンプレートページはこちらです↓↓↓
https://www.starbooks.jp/manual/data_template.php
上記からご発注サイズのテンプレートをダウンロードし、表1(表紙)用と表4(裏表紙)用の2つデータを作ります。
作ったデータ上でそれぞれ表1(表紙)と表4(裏表紙)を作成してください。
この場合、通常のデータの作り方と同じく塗り足し3mm、切れてはいけない文字やデザインは出来上がりのサイズの内側5mm以内に配置するということを意識するのをお忘れなく!
それぞれ以下のようになります。
なお、ファイル名は表1(表紙)→h1.psd、表4(裏表紙)→h4.psdなど、分かりやすくつけてください。


【ドキュメントを作成】
テンプレートを使えない環境にある場合、ご自身でドキュメントを作っていただいても構いません。
ご発注の実寸サイズ+塗り足し天地左右3mmずつ足して作成してください。
例えば文庫(A6)サイズのご発注ですと、
縦154mm×横111mm=A6サイズ(縦148mm×横105mm)+天地左右3mmずつ
(解像度は350dpiでお願いします)
になります。
あとの作り方はいつも通りです。
表1(表紙)と表4(裏表紙)の2パターンのデザインを作っていただければ問題ありません。
注意点はテンプレートを使う場合と同じです。
通常のデータの作り方と同じく塗り足し3mm、切れてはいけない文字やデザインは出来上がりのサイズの内側5mm以内に配置するということを意識してください。
こんな感じになります。
なお、ファイル名は表1(表紙)→h1.psd、表4(裏表紙)→h4.psdなど、分かりやすくつけてください。
【表1(表紙)】

【表4(裏表紙)】

背表紙の作り方
ここまでで表1(表紙)・表4(裏表紙)が作れましたね!
では、最後に背表紙を作っていきます。
背表紙は背幅によって横幅が変わります。
お客様ノートでご自身の背幅を確認してもらい、小数点を切り上げた数値を横幅にします。
縦幅はご発注サイズの縦幅に塗りたし3mmずつ(計6mm)を足した値になります。
例えば、文庫(A6)サイズだと、
縦:154mm(塗りたし3mm+A6縦サイズ148mm+塗りたし3mm)
横:ご自身の背幅の小数点を切り上げた数値
※解像度は350dpiでお願いします。
になります。
必要サイズが分かれば、その値で新規データを作成し、背表紙を作っていきます。
背表紙に関しては必ず、背表紙以外の不必要なものを同じデータ内に配置しないでください。
※トンボなども不要です。
今回は例として、背幅8.6mm(小数点切り上げで9mm)の背表紙を作成してみました。
サイズは縦154mm×横9mmで作成。掲載画像は縮小して表示しておりますが、以下のような感じになります。
なお、ファイル名はse.psdなどとわかりやすくつけてください。
【背表紙】

・プラス情報
実のところ一般に流通するものでも、背のデザインが表紙・裏表紙に回っているものは少なくありません。
同じ紙・同じ時期・同じ機械で作業をしていても、環境などに影響されて厚さが異なってしまうからです。
例えば、製本前に積み上げられていた位置の上か下かだけでも差が生じてしまいます。
基本的には若干のズレがあることを考慮し、デザインする方が安全です。
それでも、折角厚みのある本を作るなら背幅いっぱいにデザインしたい!と思うのが世の常というもの。
もしギリギリまでタイトルなどを配置するときには赤や黒などの濃い色を避け、配置する「色」を「薄い色にする」ことを心がけてみてはいかがでしょうか。

ほんのわずかに回ってしまった文字やデザインが目立ってしまうのを軽減できます。
オンデマンドの場合トナーの量が減ると、トナーが剥がれてしまったり割れたりすることも少なくなるので一石二鳥です。
まとめ
要点さえ押さえてしまえば、このように簡単に作れます!
特に小説本を作る場合、背幅が変動することが多いかと思うので、以下を守ってぜひ活用してみてください。
- 表1・背表紙・表4を別で作る場合は、表1・背表紙・表4をまたぐデザインはしない。
- 表1・表4を作る際に使用するのは、ご発注サイズの「カラー本文(単ページ)」のテンプレート。
- 表1・表4を作る際にテンプレートを使わない場合は、ご発注の実寸サイズ+塗り足し天地左右3mmずつ足して作成。
- 背表紙のサイズは、縦:ご発注サイズの縦幅に塗りたし3mmずつ(計6mm)×横:背幅の小数点を切り上げた数値。
- データは中央合わせで作成すること。
- ファイル名は表1(表紙)→h1.psd、表4(裏表紙)→h4.psdなど、分かりやすくつけること。
 STARBOOKSをご愛顧いただきましてありがとうございます。
STARBOOKSをご愛顧いただきましてありがとうございます。